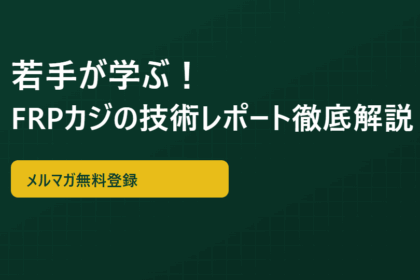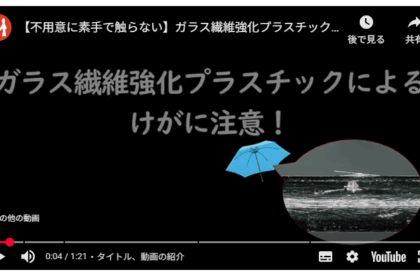株式会社 FRPカジ メールマガジン
┏┏┏┏ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ハンドレイアップGFRPの真実
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年10月1日
第五十四回:現地施工で見られるビス系ビニルエステルの硬化不良発生
~ 促進剤添加量過不足と手順違い(3液性の場合)~
<目次> ━━━━━━━━━━━━━━━━
・FRP製品の真実~現地施工で見られるビス系ビニルエステルの硬化不良発生~促進剤添加量過不足と手順違い(3液性の場合)
前回のメルマガではビスフェノール系ビニルエステル樹脂を現地施工で使用する際に起こり得る硬化不良の要因のひとつである、硬化剤添加量過不足についてご紹介しました。
今回はビスフェノール系ビニルエステル樹脂を現地施工で使用する際に起こり得る硬化不良の要因2点目として、促進剤添加量過不足と手順違い(3液性の場合)について述べてみたいと思います。
【現地施工におけるビスフェノール系ビニルエステル樹脂硬化不良の初歩的要因】
現地施工において、ビスフェノール系ビニルエステル樹脂硬化不良の初歩的要因として、
以下の6点が挙げられることは既に述べました。
‐硬化剤添加量過不足
‐促進剤添加量過不足と手順違い(3液性の場合)
‐硬化剤添加後の撹拌不足
‐強化材(チョップドストランドマット等)が水等を吸収している
‐積層下地やライニング下地の水滴等
‐樹脂塗布用の刷毛・ローラー類に水やアセトンが除去されていない
※参照コラム
第五十三回:ビス系ビニルエステルの硬化不良発生
https://x.gd/CQUKH
今回は2点目の“促進剤添加量過不足(3液性の場合)”ついて解説します。
〈2液性と3液性とは〉
一般的な不飽和ポリエステル樹脂は2液性が多く、主剤であるマトリックス樹脂と、架橋剤と触媒を含む硬化剤を混練して硬化させます。
これに対し、ビスフェノール系ビニルエステル樹脂は、
上述した不飽和ポリエステル樹脂同様の2液性のタイプに加え、3液性のタイプのものに別れます。
3液性とは主剤(マトリックス樹脂)、促進剤(触媒:コバルト)、硬化剤(架橋剤:メチルエチルパーオキサイド)となります。
ノボラック系ビニルエステル樹脂は私の知る限り3液性が基本となります。
〈硬化剤と促進剤の樹脂硬化反応における役割〉
主剤のマトリックス樹脂(ビニルエステル樹脂だけでなく、不飽和ポリエステルも同様)は、
主にビニル基と呼ばれる炭素原子同士が二重結合で結合している化学構造を有する官能基を有しており、
そこに硬化剤に含まれる不安定な過酸化物(パーオキサイド)から生じるラジカルと呼ばれる、結合が電子的に対称開裂した場合に生じる活性点が、
その官能基に攻撃することで連鎖的に結合の開裂/生成の反応が生じます。
これがFRPのマトリックス樹脂硬化反応の基本です。
促進剤はナフテン酸コバルトのような金属錯体の構造をしており液体です。
この金属錯体は触媒として機能してラジカル生成を促し、
ラジカル反応による重合、すなわち硬化反応を促進させる効果があります。
過去に当社でビスフェノール系ビニルエステル樹脂をマトリックス樹脂とするFRPの耐薬品性を評価した際、
促進剤から漏出したと推測されるコバルトイオンにより、
溶液(濃塩酸)が桃色への着色が見られたことを当社発行の技術レポート内の考察で述べています。
※参照元の当社技術レポート
JIS K 5600-6-1によるFRP耐食塗料とフッ素塗料の耐薬品性比較評価
「JIS K 5600-6-1によるFRP耐食塗料とフッ素塗料の耐薬品性比較評価」技術資料_ENG-REPORT-021
〈補助的な添加剤〉
上記以外に補助的な役割をする3種類の添加剤があります。
‐コバルトの助促進材としてジメチルアニリン促進剤D
‐夏場などの高温時に使用する硬化遅延剤
‐トップコート時に必要な空気乾燥剤としてパラフィン
ジメチルアニリン促進剤Dは、正確にはN,N-ジメチルアニリンという化合物です。
ベンゼン環に3級アミンが結合した構造をしており、このアミン中の窒素原子の孤立電子対によって、
硬化剤の過酸化物の開裂反応を引き起こされてラジカルが発生します。
これは連鎖的に起こることから、レドックス反応とも呼ばれます。
また、硬化遅延剤としては代表的なものの一つとしてp-ベンゾキノンなどがあり、
ラジカルを有する化合物と当該遅延剤中のケトン基の間で共有結合を新たに生成させてラジカルを消失させる、
ラジカル補足剤としての役割を果たします。
近年はニトロソ基を有する化合物も重合禁止剤として市販されており、
その推定反応機構から、当該化合物は従来製品より多くのラジカルを補足できると考えられています。
※参考情報
高性能重合禁止剤のメカニズムと効果 / 富士フィルム 和光純薬株式会社
https://specchem-wako.fujifilm.com/jp/polymerization-inhibitors/about.htm
パラフィンは添加によりタック性(べたつき)を低減させる効果があります。
〈硬化剤と促進剤を接触させない(3液性の場合)〉
3液性の場合はまず促進剤を混練してから硬化剤を添加します。
ここで怖いのは促進剤(コバルト)と硬化剤(メチルエチルパーオキサイド)が、
直接接触することです。
これらを直接混練させてしまうと爆発的に反応が始まり燃焼が起きます。
よって3液性の場合、促進剤と硬化剤を接触せずに保管することに最大限の注意を払う必要があります。
〈促進剤添加量過不足(3液性の場合)〉
促進剤、硬化剤の添加量については前回メルマガの内容と重複しますが、
これらの添加量は、各樹脂メーカーが最適量を気温と硬化時間の関係をデータとして公開しています。
そのデータをもとに製造会社は気温と硬化時間を考慮して添加量を決定します。
前回のメルマガでも述べた通り、
現地施工で不可避な複数回にわたる現場での計量と、
その結果に応じた規定量の硬化剤や主剤の添加と混錬という一連工程は、
すべて手作業のため計量作業や混練に誤差が生じます。
このようにして生じたわずかな添加量差異の蓄積が硬化不良の要因となります。
さらに3液性の場合、既述の通り危険性を指摘している硬化剤と促進剤の直接混錬の発生する可能性もゼロではありません。
硬化不良だけでなく、急激な反応の暴走という新たな危険因子が生まれるのです。
〈促進剤、硬化剤添加量過不足や手順違いに関して現地施工で生じる事象例〉
これは私の経験を踏まえての事例です。
3液性の代表格であるノボラック系ビニルエステル樹脂を用いるような、
高温耐食製品の補修や改修を主とした現地施工でした。
このような製品は比較的大きな構造物が多く、マトリックス樹脂の混練を複数回にわたって行う必要があります。
2液性の時と比べて混錬すべき材料が1種類増えるため、
計量された主剤に対する硬化剤、促進剤に対して計算の上で個別に計量し、
添加手順にも注意しながら混錬するという作業が2回生じます。
追加された作業内容は多くはありませんが、
過酷な現場では計量のミスや勘違いを誘発することも多く、
結果的に促進剤、硬化剤添加量過不足が生じ、
FRPの硬化が早く進みすぎる、または硬化しないという問題が生じました。
促進剤と硬化剤の直接接触という事象も経験したことがあります。
上述した通りまずは促進剤を主剤と混練しますが、
その際に促進剤を計量するのにスポイトや計量カップ等にて使用した後、
これらをアセトン等で洗浄せずに硬化剤を計量してしまうのが一例です。
未洗浄で残留した促進剤の量が少なかったため幸い火災にはなりませんでしたが、
このような手順違いは燃焼現象に直結するリスクがあります。
繰り返しになりますが、現地施工では理想的な環境で作業が進められるとは限らず、
一見して簡単な作業にも人的ミスが生じる可能性もあるのです。
今号ではビスフェノール系ビニルエステルの硬化不良の初歩的要因として、促進剤添加量過不足と手順違い(3液性の場合)について、ご説明させていただきました。
次号では硬化不良の初歩的要因として、硬化剤添加後の撹拌不足についてご紹介します。
FRPを取り扱っている方や今後取り扱いたい方にとっての一助となれば幸いです。