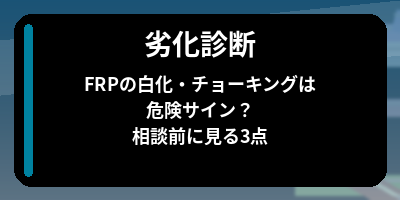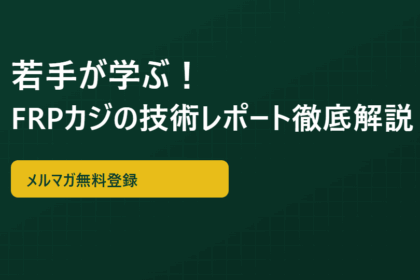株式会社 FRPカジ メールマガジン
┏┏┏┏ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ハンドレイアップGFRPの真実
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年8月4日
第五十二回:一般工業製品(一般成形品含む)と航空機製品の違いを踏まえた当社の挑戦
<目次> ━━━━━━━━━━━━━━━━
・FRP製品の真実~一般工業製品(一般成形品含む)と航空機製品の違いを踏まえた当社の挑戦
前回のメルマガではFRP製品製作でのGFRPとCFRPの違いについて、一般工業製品(一般成形品含む)と航空機製品の違いについてご紹介しました。
今回は一般工業製品(一般成形品含む)と航空機製品の違いを踏まえた当社の挑戦として、
新たなFRP業界文化の醸成に向けてFRPカジでは何ができるのか、
について述べたいと思います。ぜひご一読ください。
前回メルマガでも触れたように、
GFRPを中心とした一般工業製品と、
CFRPを中心とした航空機製品では、設計の段階でかなり異なると感じられたと思います。
安全性が第一の航空機業界の型式証明も妥当である一方、
一般工業製品で培われた実績や経験を無視すべきではありません。
航空機製品の型式証明という設計開発の基本姿勢に目を向け、
一般工業製品の設計開発に関して取り入れられる、
そして取り入れるべき観点があると私は考えています。
当社の半世紀以上にわたるGFRPを中心とした一般工業製品の製造経験と、
航空機業界での取り組みの理解を組み合わせ、
これまでよりも、より適切な設計を実現し、より安全な製品を安定して製造する、
新たなFRP業界文化の醸成に挑戦するにはどのように進んでいけばよいのかを深堀りしていきたいと思います。
GFRP業界の慣例
GFRP業界の慣例として、大きく3点に分けられます。
‐感覚論~数値データを基本とした技術的議論はほとんどない
‐経験則~過去のやり方や考え方が正しいとは限らないが、再検証を行うことは皆無
‐Web情報~技術的な“質”でいうと玉石混交の状態
新たなFRP業界文化の醸成に向け、
まずはこれらの状況に目を向けなければならないと考えます。
当社ではこの中で特に“感覚論”と“経験則”を軸とした取り組みを行っています。
それぞれについてご紹介します。
“感覚論”から実測データでの技術議論に向けた支援事業
感覚論については当社R&Dセンターでの事業として行っている、
技術評価受託がポイントとなります。
当該事業の概要は以下の通りです。
【技術評価受託】
〈材料データ取得〉
‐材料試験計画の立案と作成
‐試験片の設計と加工に対応
‐品質管理下で試験実施
‐結適正果報告書の作成と提出
〈材料特性データ解析〉
‐材料データの統計学的な解析を実施
‐静的試験、動的試験に対応
‐材料寿命予想を目的とした回帰線図の作成
上記の通り、自社の設備に加え、必要に応じた協力会社の設備を用いることで、
感覚論ではない“実測データの取得”を軸とした評価を行っています。
結果の報告を通じ、依頼いただいたお客様には貴重な実測データをご提供するとともに、
ご要望に応じて技術的な議論や更なる技術評価の企画立案支援を行っております。
取得したデータは構造設計だけでなく、
市場問題の原因究明など幅広い目的に活用いただいております。
※当社関連ページ
“経験則”の裏付けを行うことで自社技術の研鑽を継続
当社ではFRP業界で経験の長い技術者もおりますが、
その経験に過度に依存することなく技術的な事実は何かを突き詰めることを、
自社の技術戦略として掲げています。
この取り組みにおいては当社の本社工場の技術者だけでなく、
R&Dの技術者も一緒に議論の上で技術テーマを立案し、
評価を行っています。
ここでは経験則の裏付けに関する当社の技術テーマのうち、2つほどご紹介します。
GFRPの手加工に適したドリル形状や加工条件は何か
手加工によってGFRPに穴あけ加工を行う場合、
経験則で修正が行われた当社オリジナルのドリル形状がありました。
ただ、なぜこの形状が妥当なのかについては検証が不十分であったため、
ドリルの形状と加工条件に関し、2つの評価を行いました。
当社オリジナル形状のドリルは摩耗量が少ないことを確認
最初に評価したのは当社設計のオリジナルドリル形状に、
どのような強みや特徴があるか、ということでした。
市販ドリルと当社オリジナルドリルでGFRP平板に対して複数の穴あけ加工を行った結果、
後者の方がドリルの摩耗が少なく、耐久性が高いことを、
非接触形状測定機の一種である三次元デジタイザーによる加工前後の形状変化量を評価することで明らかにしました。
※関連する当社技術レポート
自社加工した FRP 穴加工用 Drill の形状と加工物の X 線 CT 評価/ ENG-REPORT-005
ドリルの逃げ角と加工回転数を変更することで加工時のGFRP発熱を抑制することを発見
ドリルの形状設計を当社でより適切に行うにあたっては、
どのような形状パラメータがドリルの最適化に必要かを明らかにする必要がありました。
このような評価には学術界の支援も必要と考え、
大学との共同研究の枠組みにおいて評価を推進しました。
評価ではドリル形状パラメータの中から“逃げ角”に着眼し、
複数の角度を有するドリルを実際に試作してGFRPを加工することで、
加工時のトルク、スラスト、温度変化に加え、
加工くずのTG/DTA分析によりマトリックス樹脂の残重量を評価しました。
結果、逃げ角が大きく、かつ加工時の回転数が大きいほうがGFRPの加工による熱分解を抑制することを明らかにしました。
一般的には逃げ角が大きいほど、回転数が大きいほど加工時の発熱が大きく、
GFRPの熱分解が進むと考えられましたが“逆の結果”になったことは大きな発見でした。
大学教授との議論を通じ、本現象は発熱に伴うGFRPの弾性率低下と、
加工側面の形状復元による加工側面のドリルとの接触によるスラスト低下であることを明らかにし、
経験則をより適切にするには逃げ角と加工時の回転数の変更がキーになることがわかりました。
※関連する当社技術レポート
ドリルの逃げ角がGFRP加工熱に与える影響とその評価/ ENG-REPORT-022
今号では新たなFRP業界文化の醸成に向けてFRPカジでは何ができるのか、
という題目について、当社が実際に挑戦していることについて、ご説明させていただきました。
次号では“経験則”の裏付けを行った別の技術テーマについてご紹介します。
FRPを取り扱っている方や今後取り扱いたい方にとっての一助となれば幸いです。