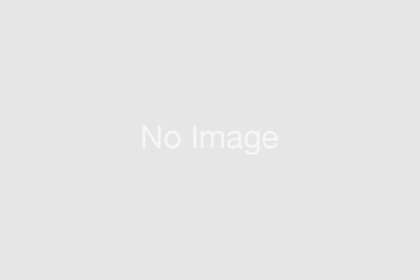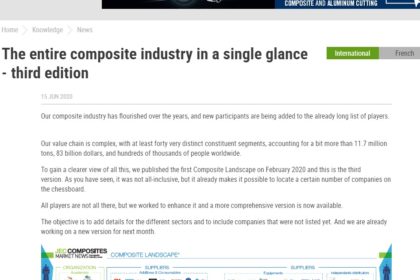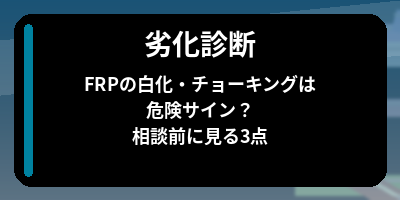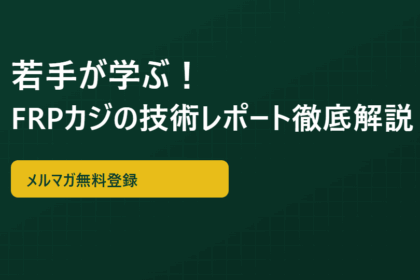風力発電ブレード落下事故から学ぶ、FRP構造物の見えない劣化のリスクとその対策 【FRPエンジニアによるコラム】より
2025年5月2日、秋田県秋田市の日本海に面した新屋海浜公園に隣接する風力発電にて発生した風力発電のブレード破損・落下事故は、多くのメディアで取り上げられ、再生可能エネルギー関連企業や関心のある方々に衝撃を与えました。
不幸な事に落下した風力発電ブレード破片の近くに男性が倒れていて、その後、死亡が確認されました。
FRP(繊維強化プラスチック)構造物に携わる私たちから見ると、この事故は決して偶然ではなく、予見可能なリスクであった可能性があります。
風力発電ブレードに多く使われるFRPの劣化は外観からはわかりにくい
風力発電のブレードは、多くがFRP製です。軽量かつ高強度で腐食に強いFRPは、巨大構造物の回転部材に最適ですが、その一方で
「見た目では劣化が分かりにくい」
という課題を抱えています。
紫外線、風雨、雷、温度変化、振動…。これらの複合的な環境負荷は、目視や簡易打音では検知できないFRPの破壊につながる内部劣化を引き起こすことがあります。
特に日本のような四季があり、台風や積雪といった過酷な環境に置かれたブレードは、設計寿命を迎える前でもこの劣化が進行することが珍しくありません。また、設計要件基準が前出の環境負荷を十分に考慮できておらず、不十分の可能性もあるでしょう。
FRPの破壊を未然に防ぐには
ここで重要なのは、「劣化が見つかってから」ではなく、「見つかる前に診断を行い、劣化予兆をいち早く捉える」ことだと考えます。
FRPブレードの表面と裏面が離脱する事例も
私は2023年10月に中型風力発電ブレードを現地で設置したままで、補修可否の確認依頼に応じて視察に行きました。そして、驚くことに設置から2年から3年でブレードの先端部が裂けてくる事案が多く発生すると、現地担当者からうかがいました。
先端が裂ける事象は、ブレードの翼面形状を形成する上下のスキン構造材の接合部が破損することにより起こったと考えられます。
このような接合部は、金属などの異種材との組み合わせ、複雑形状を有する構造部材同士を一体化する際に必要となります。接合部の破壊は突然起こるとは限らず、最初は接合面の微小な剥離から始まることもあります。
このような初期の剥離を目視検査だけに限らず、超音波や浸透探傷などの非破壊検査で捉えられる可能性があります。これは既述の“診断”の一例です。
一般工業製品用途のGFRPに関する慣習がFRP破壊リスク低減の取り組みの足かせとなっている側面も
新屋海浜公園で破壊した風力発電ブレードの映像を見ましたが、大型のためブレード1枚は長さ50~70メートル程度、重さも20~30トン程度のものが主流と報道されています。破壊の瞬間も完全に根本からちぎれるように落下していました。
今回の風力発電設備を保守点検する日立パワーソリューションズのHPに保守点検についての記載や動画もあり、人による徹底した点検だけでなく、ドローンとAIを組み合わせた検査など、現在実施可能と考えられる中で適切な方法にて行われていると感じました。
しかし、ここからは当社も直面している問題とリンクいたしますが、2次災害的とは言え、死亡者が出たことを重く受け止めなければなりません。ここで航空機業界の考え方が次の一歩を踏み出すヒントになるかもしれません。
航空機業界では構造部材に関してFRPに限らず、人的被害リスクを限りなくゼロにすることを最優先に設計からものづくり、そして運用開始後もオーバーホール等の点検を徹底管理して行いますが、当社も含め、GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)を中心とした一般工業製品用途の場合、用途に潜むリスク回避の設計思想や管理された製造工程や点検よりも、製品製造時のコストや効率が最優先になっています。
この“慣習”に問題が潜んでいると考えます。
今回のような風力発電ブレードが定期点検されていたにもかかわらず、想定寿命よりも短いであろう設置14年で破壊したことは、風力発電ブレードも前出の慣習に則り、一般工業製品向けの流れで作られたのではないかと強く感じました。
もしそれが事実だとすれば、コストと効率に偏重した慣習が今回の人命を奪った可能性もあります。これまで当たり前と考えられた慣習を“変えなければならない状況”になっているのではないでしょうか。
FRPに関する慣習を変えることへの当社の挑戦
当社では、長年にわたり一般工業製品を想定した耐食FRPの劣化診断の取り組みを継続し、様々な経験に基づいて技術を向上させてきました。
目視、触診、硬度、超音波、浸透探傷など、複数の診断技術を組み合わせることで、FRP構造物の健全性を総合的に評価しております。具体的には国内の化学プラント、上下水道施設、貯槽タンク、さらには海外企業工場での技術評価案件でも、“見えない劣化のリスク”をあぶりだすことを中心に、劣化診断を行ってきました。
今回の事故を「他山の石」としないために、風力発電に限らず、FRPを使用している施設の管理者の方にはぜひ一度、人的被害を想定した設計の徹底に加え、FRP専門の診断の重要性を再確認していただきたいと思います。
安全・安心を守る第一歩は、「まだ大丈夫」ではなく、「いま診断しておこう」 という発想により、劣化の兆候をいち早く捉えることに違いありません。