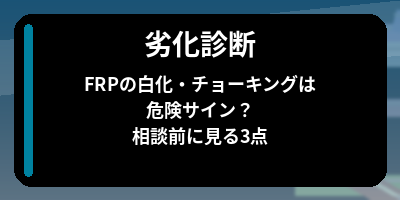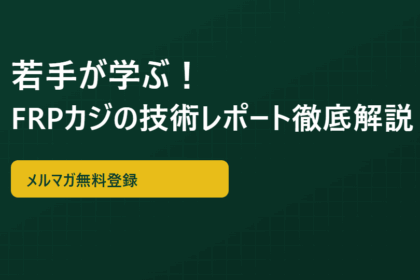株式会社 FRPカジ メールマガジン
┏┏┏┏ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ハンドレイアップGFRPの真実
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年4月1日
第四十八回:FRP製品の真実~ FRP100%リサイクルへの挑戦:FRP100%リサイクルに至るまでの過程4(FRP100%リサイクルによる当社の循環型社会実現への挑戦)
<目次> ━━━━━━━━━━━━━━━━
・FRP製品の真実~FRP100%リサイクルへの挑戦: FRP100%リサイクルに至るまでの過程4(FRP100%リサイクルによる当社の循環型社会実現への挑戦)
前回のメルマガではFRP100%リサイクルに至るまでの過程3として、
産業廃棄物処理収集運搬・積替許可取得からFRP100%リサイクルサプライチェーン構築までついてご紹介しました。
今回はFRP100%リサイクルへの挑戦: FRP100%リサイクルに至るまでの過程4として、
FRP100%リサイクルによる当社の循環型社会実現への挑戦についてご紹介します。
【リサイクルサプライチェーン構築による今後のFRPの取り扱いについて】
ここからは前回メルマガと重複しますが、
当社の既存事業の一つに“老朽化設備の長寿命化対策支援”があり、
本事業においてFRP構造物の長期利用に向けた“劣化診断”を行っています。
※老朽化設備の長寿命化対策支援
劣化診断の結果に応じ、
必要な劣化箇所だけに注力してFRPのオーバーレイを中心とした補修を実施することで、
FRP構造物の長寿命化を進めています。
しかし中には補修を行うことによる機能回復が困難な場合もあり、
そこでは補修不可の診断結果となります。
従来はこのような結果となった構造物は廃棄していましたが、
今回構築したFRP100%リサイクルのフローにより、
廃棄物をサーマルリサイクルとマテリアルリサイクルを組み合わせた処理を適用することが可能となりました。
つまり、劣化診断からリサイクルという道筋がFRP構造体に見出せたことになります。
【現在主に行われている劣化したFRP構造物の新規入れ替えは選択肢の一つ】
FRP構造物で劣化が見られる箇所の典型的な例として、FRP製耐薬品貯蔵タンクやスクラバー、配管等があります。
これらにおいて液漏れや割れ等の問題は増加しており、特に製造から10年経過後に顕著に現れています。
この場合、メーカーが調査を行いますが、タンク内バーコル硬度値や触診により、補修は不可能と判断されるケースがあります。
もちろんこの判断を非難するわけではありません。
また、新規タンクに入れ替える事が最大のリスクヘッジであり、妥当な選択肢の一つであることは理解しています。
ここでのポイントは、新規設備への更新が行われる際の当社が貢献できることが何かだと思います。
このようなFRP構造部材の新規入れ替えの場合、
例えば当社の構築したFRP100%リサイクルサプライチェーンのルートに乗せ、
徹底分別の上、廃棄予定のFRPに対してサーマル/マテリアルリサイクルを実施するのが一案です。
同時に、FRP構造物全体で見た場合に補修、改修による長寿命化は本当に不可能なのかを判断する劣化診断も、
循環型社会の実現への重要な方向性の一つと考えます。
これは、全体を更新するよりも必要個所に対して補修、改修を行うことで既存構造物を再利用する方が、
消費する材料、製品の輸送等のトータルでの温室効果ガス排出量が少ないといった、
環境負荷が低減できると期待されるためです。
【FRP100%リサイクルによる当社の循環型社会実現に必要なのは実データの蓄積】
ここまでご紹介した通り、FRP100%リサイクルについてサプライヤチェーンの構築までは概ね到達できたと考えています。
FRP構造物の劣化診断と必要に応じた補修、改修による長寿命化、
そして寿命を迎えたFRP構造物のリサイクルという二本柱が軸となります。
しかしこれは当社の目指す
「循環型社会の実現」
という目標に対しては道半ばとの理解です。
何故ならばFRPは使用する強化繊維/基材構成とマトリックス樹脂の種類、その比率(Vf)、
そして積層や成形方法、さらには成型後のFRPが暴露された溶媒/温湿度/荷重負荷環境とその時間によって、
異なる残寿命を示すためです。
すべてのFRP構造物に対する寿命を適性判断する万能解は存在しないのです。
その中でも当社は、これまでの半世紀以上に及ぶFRPの設計、製造、加工の経験を踏まえ、
FRPがどの程度の寿命を有するのかの技術評価を継続しています。
一例として、50年屋外曝露されたFRPの特性評価を行ったものでは、
引張弾性率は2割程度、引張強度は半分程度まで低下するという現象も確認しており、
これはFRP構造物の補修、改修する上で大きな指標にもなっており、
また今後の当社におけるFRP寿命評価の参考データの一つになっています。
※「50年屋外曝露されたFRPの特性評価」技術資料_ENG-REPORT-015
循環型社会実現には上述の例も含め、更なる実測データの蓄積が必要と考えています。
一品一様のFRP特性を念頭に実測データや疲労特性データを蓄積し、
FRP構造物の寿命について適切な判断をできるよう、
当社の技術データベース強化を推進してまいります。
このような取り組みを通じ、FRP構造部材で使えるものはできるだけ長く、
そして使用安全に懸念が認められる場合は新規への更新を促し、
使用済みのFRP構造部材は徹底分別の上でリサイクル工程に回すという流れを構築することが目標です。
前出の評価はFRPに特化した研究開発を行っているR&Dセンターで実施しており、
FRPに関する技術評価結果を中心に、技術レポートやコラム、メルマガで積極的に技術情報発信しています。
当社の取り組みの一例としてご覧いただければ幸いです。
当社本社工場のFRP製造と補修、改修技術とR&Dセンターの研究開発の両輪により、
当社はFRPに関する循環型社会実現に一歩近づいたと考えます。
今後も既存事業とFRP100%リサイクルの組み合わせ方について、
当社は継続検討して参ります。
今号ではFRP100%リサイクルへの挑戦: FRP100%リサイクルに至るまでの過程4として、FRP100%リサイクルによる当社の循環型社会実現への挑戦をご紹介しました。
次号では初心にかえりFRPの基本的な特性などについてご紹介します。
FRPを取り扱っている方や今後取り扱いたい方にとっての一助となれば幸いです。